宮城県立ろう学校訪問記
以前,校長先生から,朝日新聞に掲載された「PDA(Personal
Digital Assistance。個人用の携帯情報端末)を使った授業実践」が紹介されたことのある学校です。上野7時2分発のはやて1号で,都庁の山崎さんと待ち合わせ,学校に到着したのは9時20分頃。授業はすでに始まっていました。
今回の授業については,あらかじめ,大阪生野高等聾の前田先生が主催するメーリングリスト(以下,MLと省略。2月14日現在,生野高聾・葛飾ろう・宮城ろう・長岡聾・岡山聾・長野聾・岡崎聾・大阪市立聾・堺聾・生野聾・奈良ろう・京都聾・野村総研・国立特殊教育総合研究所が参加)で伺っていたので,以下,そのMLから引用します。
○ 2月6日
中村先生おはようございます、前田@生野高等聾です。
FOMAを借りる手配が出来ました。
一応、2月13日ごろから1週間を予定しています。
そのあたりで、そちらのご都合を教えていただければ有難いです。
14日には、伊藤先生もそちらに行かれるとお聞きしていますので、
伊藤先生にも見ていただけるといいかな?とも思っています。
西成高校の先生からは、
>
>
>
>
>
>
とコメントをいただいています。
○ 2月7日 宮ろうの中村です。(途中,省略)
生徒も初めて使うので,自己紹介や学校紹介などをして,
どのくらい通じるかを試してみたいのですが。
こちらは高等部一年生で
>
詳しくは見ていないので,よく分からないのです。
週末,土日に調べてみたいと思います。
パソコンへのライブ配信は可能のようですので,
それを利用して,ということになるのでしょうか。
ただ,ライブ配信には,通信・放送機構への予約が必要で,
スケジュールを見ると,二月は結構いっぱいだったような気がします。
>
>
> http://www.cec.or.jp/books/H09seika/koumyo.html
> 携帯というか移動端末にも興味はあります。>
伊藤先生,すごいですね。
私も,
伊藤先生にも,来校した時に,借りている機種を実際に見ていただき,
いろいろとアドバイスをもらえればと思います。
○ 2月13日 宮城ろうの中村です。
明日の授業は,高等部数学1の個数の処理のなかから,偽コインを探せという題材で
授業をします。
偽コインを効率良く見つける為の手順を探すことが目標ですが,考える為の道具とし
て
ここでのねらいはもう1つあります。
偽コインを見つける手順を,どのように記述するかです。
聾学校の生徒は,数学的用語をうまく使えず,操作的な用語を多く使って表現してし
まうことが多いようです。
操作的な用語から数学的な用語への移行を,
今回はそのための第一歩と考えています。
もしお気付きの点などあれば,ご助言頂ければ助かります。
明日,よろしくお願いします。
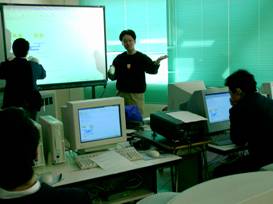
宮城県立ろう学校のホームページにも掲載されている,中村先生手作りの教材を使って数学の授業をされていました。画面にタッチするとマウスと同様の操作ができるデジタルボードを使っておられました

FOMAを使って学校インターネット経由でビデオ配信したものを投影する予定だったそうですが,不調でこの日は実現しませんでした。デジタルボードかと思ったら,通常のホワイトボードに小さなプロジェクタ(葛飾で購入したものよりさらに小型のもので,30万ほどとか)で投影していたようです。

FOMAを使って生野と直接交信。相手の画面の他に,自分の画面も入る。ビデオ出力端子がないので,生野では,FOMAの画面をビデオカメラで撮影しプロジェクターで投影したようです。生野の前田先生曰く,「大阪の学校インターネット参加校の先生とTV会議をしました。CU-SeeMeを使っていますが、FOMAの画像のほうが断然滑らか」とのことです。

生野高等聾学校のFOMAの画面。前田先生から送付して頂きました。
授業を見せて頂いたあと,校長室で,教頭先生・教務部長さんから学校の概要を伺ったあと,再び,授業のあったワープロ室に移動し,中村・鎌倉両先生から,色々お話しを伺う事が出来ました。宮城ろうでは,全校にLANを配線し,すべての先生がパソコンを使える状況にまでなっておられるようです。校内配線図と共に,
・
聾学校におけるインターネットを活用した共同学習の実践と評価
〜コミュニケーション活動の促進と主体的学習の構成〜
・
聾学校におけるインターネットを活用した指導の現状と課題(「ろう教育科学」
・
聾学校におけるインターネットを活用した数学共同学習の有効性(「日本教育工学雑誌」
を頂きました。
コンピュータのネットワークも人のネットワークも基本は同じ。つながることで楽しい事も増えるが,それに比例するかのようにトラブルも倍加する。仙台駅近くで昼食を終えたあと,「色んな立場の人が,それぞれの立場で頑張るわけですが,基本は子どもたち…」とは,学務部の山崎さんの弁。こういった地道な努力の積み重ねが,ろう教育の,ひいては日本の教育界全体の「学びの共同体」の創出と拡大につながるといいなぁと思いながら帰校しました。
文責:高等部・伊藤守 2月14日